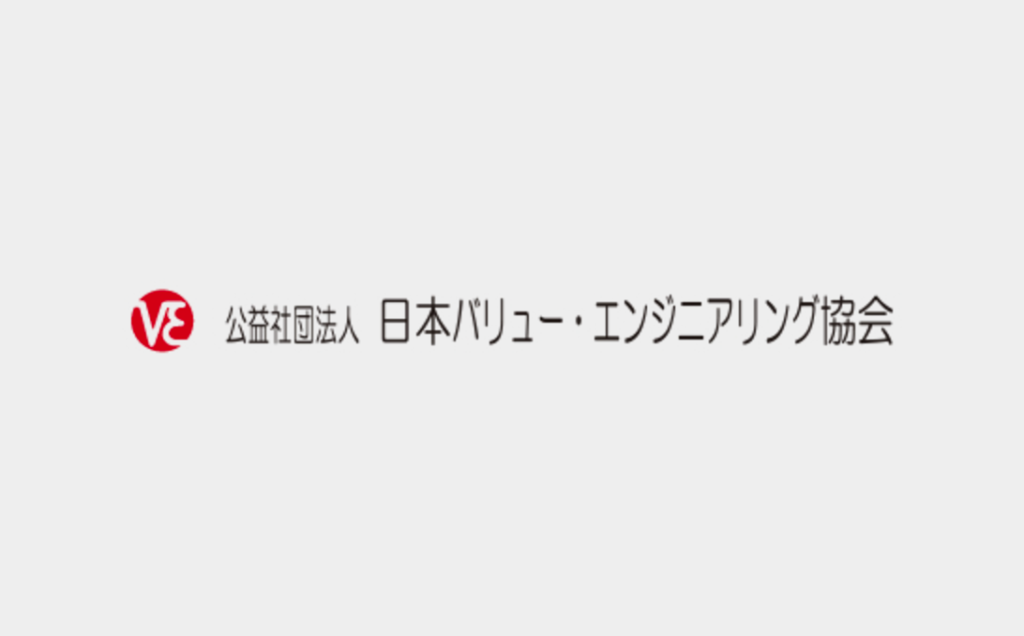-

構成部品相関図の探究とそれを活用した機能系統図作成テクニックの考案
VE実施手順において機能の整理段階で機能を目的-手段の論理に基づいて機能系統図を作成する。この機能系統図は設計の考え方の理解やアイデア発想の誘発などに寄与し、次のステップである機能評価を行う上での材料となる。ゆえに機能的研究法の重要な位置づけといえよう。 このためその作成過程及び完成度は機能的研究における活動成果に大きく影響を及ぼす。 この機能系統図の作成においてはVE活動メンバーの知識・経験・ス -

狩野モデル活用によるサービス価値評価技法の開発
不人気産業の代表であると言われている宿泊業や飲食業は、接客サービス業の代名詞的な業種であるが、コロナ禍において人々の移動制限により、経営的にも厳しさが増している。それは、従事者自身の感染リスクとも相まって、一層、その存在価値が危ぶまれている。では、これらの業種は今後、衰退、あるいは消滅していくのであろうか。テイクアウトや宅配需要に対する対応、感染対策を講じた設備投資、政府による数々の支援で、収束を -

簡易版のVE ワークショップ開発と適用実践
VE は、世の中の製品やサービスなど、全てを改善対象にでき、その効果も絶大である。より広い領域で適用され、より大きい改善効果を期待し、VE を積極的に導入する企業も少なくない。VE を導入する企業にとって、その普及活動は極めて重要となる。社内への普及がうまく行かなければ、VE の導入や普及活動に掛かる投資が無駄となる。とはいえ、導入後数年間はVE 専門家が不足するため、多種多様な対象テーマの規模や -

機能思考と品質思考を融合した詳細評価(技術性の評価)プロセスの考察
機能思考が特徴の1つであるVE(Value Engineering、以降VE と記す)は、必要な機能を確実に達成することを目指した活動により、使用者が思いもよらないような革新的な製品や新たな実現手段を有した製品が実現可能となる方法論である。 しかし、VE ジョブプランにおける代替案作成段階の詳細評価では、代替案の設計内容が具体化されるため、プロジェクトメンバーは、品質思考(原因-結果の論理で徹底的 -

デジタルVEワークショップの試行と今後の展望
コロナ禍において、イベントや会議の開催には十分な感染症対策が求められる。VEは多人数が対面式で参加するワークショップを行うため、密となるイメージが避けられず、2020 年度はVEの実施そのものを躊躇してしまう傾向が見られた。 しかしながら、プロジェクトを円滑に進めるためには、コロナ禍においても丁寧な意見交換や議論の場が必要である。 今回、公共事業を対象に、WEB会議や少人数会議を組み合わせ、感染リ -

設計ノウハウ伝承にVE活動を上手く活用するための提案
自社製品を保有する製造業において、企業の持続可能性を確保することは重要であり、自社製品の設計ノウハウの伝承は、企業の持続可能性を確保するための課題の一つである。そこで、機能定義を適切に実施することによる①製品の特有情報などを共有できる、②製品が果たすべき機能や制約条件を明確にできる、③設計の考え方を理解することができる、などの期待効果より、設計ノウハウ伝承のためにVEを適用するケースが増えている。 -

FAST とTRIZ を組み合わせた現場作業の組織的改善
従来の現場作業の改善は、現場主体の小集団チームにて実施されており、それに活用される手法としては、IE やQC が主体的に用いられてきた。そしてこの活動は、確実に成果をあげてきた。しかしながら近年の少子化による現場作業者の減少とICT の急速な進歩により現場作業の改善方法の変革が必要となってきている。筆者らは、現場作業の改善を組織的知識創造のSECI モデルの概念にしたがって実施することを推進してい -

製造VEプロジェクト活動 に用いる機能定義の動詞調査
「機能定義は、機能的研究の基礎でありVE活動の成果と効果に影響を与える重要なステップである。」 1) これは、VE研究論文「機能定義についての考察」のはじめに記されている一文である。また、この論文の終わりに「機能定義用語の選択と標準化に(中略)ついて今後いっそう実践活動にむすびついた研究を進める必要がある」1)と記されている。 このように、機能定義に使用する用語、特に動詞の選択は、VE活動を効率的 -

製品開発の仕様検討段階における情報収集手法の適用とその考察
製品の価値向上の形態の一つに「機能の向上」、すなわち「より優れた機能を持った製品を使用者に提供する」方法がある。そのためには的確に「使用者の必要とする機能」を理解し、その要求を上回る機能を提供しなければ、高い顧客満足を得てその価値を認められることはない。 本論文では、VE対象の情報収集のステップでの「体験法」「生活研究(観察法)」、機能の定義のステップで「シナリオライト法」を適用した事例をもとに、 -

VE成果拡大につながるアイデア発想活動の提案と実践
VE適用が製品やサービスの価値向上に成果をもたらすことは、VE全国大会等で紹介される様々な事例が示すとおりまぎれもない事実である。より大きなVE成果を得るためには代替案のもととなる優れたアイデアが不可欠であり、アイデア発想力を強化することはVE成果の拡大に直結する。 本論文では、VE適用によって得られる成果をこれまで以上に拡大するために、アイデアを闇雲に数多く発想するのではなく、価値向上に寄与する
VEテクニック– tax –
検索する項目を選択してください。